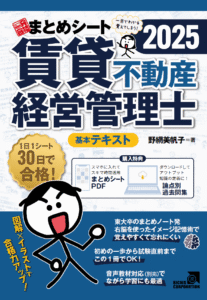今日は、平成30年度 第17問について解説します。
敷金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 賃貸借契約書に借主からの敷金の相殺について禁止する条項がない場合、借主は契約期間中、敷金返還請求権と賃料債務を相殺することができる。
② 賃貸借契約書に敷金の返還時期について何らの定めもない場合、借主は敷金の返還を受けるまでの間、建物の明渡しを拒むことができる。
③ 借主の地位の承継があったとしても、特段の事情のない限り、敷金は新借主に承継されない。
④ 賃貸借契約書に敷金によって担保される債務の範囲について何らの定めもない場合、敷金によって担保される借主の債務は賃料債務に限定され、貸主は原状回復費用に敷金を充当することはできない。
解説
敷金に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
賃貸借契約書に借主からの敷金の相殺について禁止する条項がない場合、借主は契約期間中、敷金返還請求権と賃料債務を相殺することができる。
×不適切です。
敷金返還請求権とは、借主が貸主に対して敷金の返還を請求する権利のことをいい、賃貸借契約が終了し、借主が建物を明け渡したときに発生します。
つまり、賃貸借契約書に借主からの敷金の相殺について禁止する条項の有無にかかわらず、借主は契約期間中、敷金返還請求権と賃料債務を相殺することはできません。よってこの選択肢は不適切です。
ただし、貸主は、賃貸借契約の期間中であって建物の明渡し前であっても、借主に賃料の不払いや損害賠償などの債務がある場合には、いつでも任意に敷金をその弁済に充当することができます。この点と混同しないよう注意したいですね。
選択肢 ②
賃貸借契約書に敷金の返還時期について何らの定めもない場合、借主は敷金の返還を受けるまでの間、建物の明渡しを拒むことができる。
×不適切です。
敷金返還請求権が発生するのは、賃貸借契約が終了し、物件の明渡しが完了したときです。
敷金の返還と明渡しは、明渡しが先履行となります。
つまり、賃貸借契約書に敷金の返還時期について何らの定めもない場合、借主は敷金の返還を受けるまでの間、建物の明渡しを拒むことはできません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ③
借主の地位の承継があったとしても、特段の事情のない限り、敷金は新借主に承継されない。
〇適切です。
借主が賃借権を譲渡するなどして地位を承継した場合でも、敷金は新しい借主に承継されません。
原則として、貸主は旧借主からの敷金返還請求に応じることになり、新しい借主は新たに敷金を預け入れるのが一般的です。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
賃貸借契約書に敷金によって担保される債務の範囲について何らの定めもない場合、敷金によって担保される借主の債務は賃料債務に限定され、貸主は原状回復費用に敷金を充当することはできない。
×不適切です。
賃貸借が終了し、建物を明け渡す際に債務不履行がある場合には、当然にその弁済に充てられ、差し引いた残額が借主に返還されます。
敷金によって担保される借主の債務の範囲は、賃貸借契約から生じる一切の金銭債務です。
つまり、賃貸借契約書に敷金によって担保される債務の範囲について何らの定めもない場合、敷金によって担保される借主の債務は賃料債務に限定されることなく、賃貸借契約から生じる一切の金銭債務であるため、貸主は原状回復費用に敷金を充当することもできます。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。